
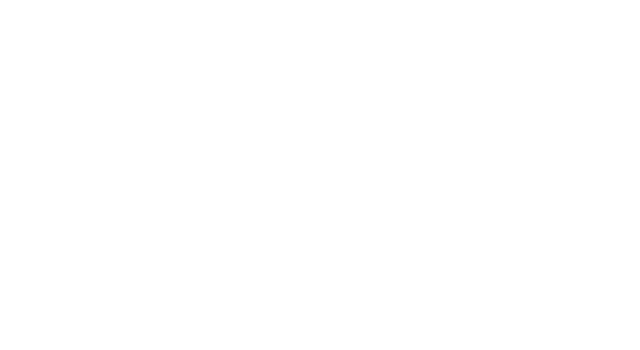
暑さや湿邪から身を守る「じゅんさい」 じゅんさい
じゅんさいはアジア、北米、オーストラリア、アフリカなど世界中に広く分布しており、日本では秋田と山形を主産地として淡水の沼や溜池に自生するスイレン科の多年生水草です。じゅんさいの旬は初夏の6月から夏にかけてです。
かつては全国で見られる植物でしたが、きれいな水でしか生息できず、水質汚濁や農薬などに敏感で栽培方法を少しでも誤ると簡単に死滅してしまうため、現在では希少な食材です。
5、6月頃の若芽・若葉は食用となり、柔らかく透明のゼリー状でぬめりで被われており、新鮮なものほど味が良いとされています。つるんとした喉越しとぷるぷるの食感が特徴です。
じゅんさいの効能・効果
じゅんさいの成分は90%以上が水分でできており、その他には食物繊維、ビタミンB2、亜鉛などを含みます。じゅんさいのぬめり成分は「アルギン酸」という食物繊維のひとつです。
- コレステロールの排出
ぬめり成分であるアルギン酸は、腸内にあるコレステロールを体外に排出するため、脂質異常症や動脈硬化の予防に働きかけます。 - アンチエイジング
昔から生命力の源である腎を補う食材とされ、その音が「若芽」「若女」と通じることから、老化を防ぎ、若返りの薬として使われてきました。実際にじゅんさいにはお茶に匹敵するほどのポリフェノールが含まれていることが知られています。 - むくみの防止
じゅんさいには利尿作用があり、体の余分な水分を外に出す働きがあります。
独特のぬめり成分はガラクトース、グルクロン酸、フコース、マンノースなどの多糖類とされています。
効能 :熱を取り除き、身体に害を与える作用を排除する。高熱・悪熱、多汗・四肢痙攣、麻痺、できもの。脾胃の気を下ろして吐き気を止める。
じゅんさいの主な栄養成分(1パック 200g当たり)
・ 食物繊維・・・2g
・ タンパク質・・・0.8g
・ ビタミンA ・・・4μg
・ ビタミンE ・・・0.2mg
・ ビタミンK ・・・32μg
・ ビタミンB2 ・・・0.04mg
・ 葉酸 ・・・6μg
・ ナトリウム ・・・4mg
・ カリウム ・・・4mg
・ カルシウム ・・・8mg
・ マグネシウム ・・・4mg
・ リン ・・・10mg
・ 脂質・・・0.0g
じゅんさいの東洋医学的側面
・寒熱:涼(穏やかに体の熱を冷ます)
・五味:甘味、寒性
・臓腑:肝、脾
・毒性:なし
湿邪が滞らないよう、余分な水分を汗や尿として排泄させます。
じゅんさいの栄養素を上手に摂るための保存方法と調理方法
じゅんさいには、生のままパック詰めされているものと、水煮にしてからパックや瓶づめにされているものがあります。
生のものは鮮やかな緑色をしていて、水煮のものは赤みがかった色をしています。
生のじゅんさいは、鮮度が落ちる前に早めに食べ切るようにしましょう。じゅんさい鍋にして頂くのもお勧めです。
すぐに食べない場合は冷蔵保存するとよいでしょう。
この場合はじゅんさいを水で2~3回ほど洗って水気を切り、沸騰したたっぷりの湯で鮮やかな緑色になるまで茹でます。茹で上がりはすばやくザルに取り、氷水のような冷水で冷やします。そのあと小分けにして冷蔵庫で保存ください。
じゅんさいは淡泊な味わいなので、軽く湯通ししてそのままいただく他、酢の物や汁物に入れたり、お料理のトッピングに添えたりなど、いろいろなレシピで楽しめる食材です。








