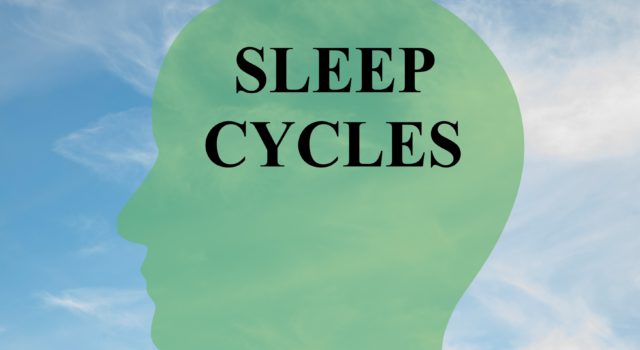
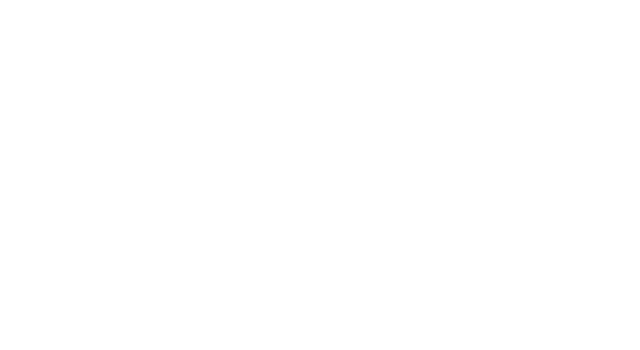
睡眠とホルモンの関係
外来をしていると世の中には睡眠が取れなくて困っている人がたくさんいることに気づかされます。
実際に睡眠導入剤を飲んでいたり、昔処方された睡眠薬から離れられなかったりなどお悩みは多岐に渡るようです。
ベンゾジアゼピン系の睡眠薬や抗不安薬を長期にわたって使用していると、集中力、記憶力や認知などの脳の機能が落ちてきてしまうことも知られています。
満足した睡眠を取れることと寿命は相関しているという報告もありますし、乳がん、心筋梗塞などの血管系の病気や糖尿病などの生活習慣病は睡眠不足や睡眠の質の低下と関係していることが知られています。
ショートスリーパーと言って短時間の睡眠で事足りる人もいますが、やはり身体のシステムを円滑に進めるためには良質な睡眠は必要不可欠だと思います。
最近ではアップルウォッチなどのデバイスで、レム睡眠とノンレム睡眠の比率が簡単にわかるようになっています。
寝入りが悪いのか、寝ている途中に睡眠が浅くなっているかなどを調べてみて自分に合ったライフスタイルを整える必要があると思います。
寝入りが悪い人で多いのがメラトニンという睡眠のホルモンがうまく働いていない人。
こうした人は朝起きた直後に30分ぐらい日に当たって明るい環境(6000ルクス)にいることが重要です。
そして寝るときは可能な限り寝室を暗くして、スマートフォンやテレビなどの明るい光を見ないようにすることによって概日リズムという睡眠サイクルが回復し始めます。
多くの場合は2週間から1ヶ月ぐらい、徹底的にこのように朝と夜の習慣を変えることで睡眠の質が上がってきます。
それでも改善しない場合は栄養障害によってメラトニンが作られていないことも考える必要があります。
メラトニンはトリプトファンというアミノ酸が原料となって体内で合成されていきます。
またビタミンB、葉酸、鉄、マグネシウムなどの栄養素がないと体内で合成されない可能性があります。

睡眠の満足度は低い人では成長ホルモンや女性ホルモンが分泌されていないという報告もあります。
成長ホルモンは寝る前にアルコールを飲むと分泌されにくくなります。
寝起きに疲れが取れていない人は、眠られないからと言ってウイスキーを飲んだりしないでお休みしないでくださいね。
他にもカフェインが含まれているようなコーヒー、紅茶などは満足した睡眠が取れていない時間がある時は量を減らしたり、飲むのを止めたりした方が良いと思います。
また日中に筋トレをすると夜間の成長ホルモンの分泌量が増えます。正しい運動後のビール、ワインなどのアルコールを飲んでしまうと成長ホルモンの分泌が抑えられてしまうかもしれないので我慢が必要です。
睡眠の質があることはアンチエイジングのみならず健康寿命を伸ばすためにも非常に重要な概念です。
毎日は無理でも週に2回や3回は理想的な睡眠を取れるように心がけましょう。
今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。
もう少し睡眠と食欲についてお知りになられたい方はこちらをご覧ください。
食欲をつかさどるホルモンであるレプチンやグレリンの話をDr.河村と対談しています。
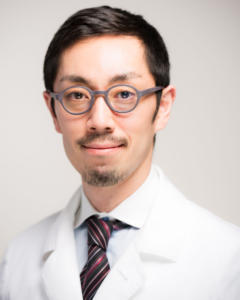
〔大友“ピエール” 博之〕
日本のみならずロサンゼルス、フランクフルト、香港、バンコクに拠点を持ち、個別化医療(precision medicine)を実践している。免疫栄養学に基づいた食事指導、ホルモン補充療法、運動療法を取り入れた治療で定評がある。
・ 医師 日本抗加齢医学会専門医 / 欧州抗加齢医学会専門医 / 日本麻酔科学会専門医
・ 西洋薬膳研究家、シェフドクターピエールとしても活躍中
・ 渋谷セントラルクリニック代表
・ 一般財団法人 日本いたみ財団 教育委員
・ 料理芸術や食の楽しみといった価値感を共有するシェフなどが集う日本ラ・シェーヌ・デ・ロティスール協会のオフィシエ
・ ワインにも造詣が深く、フランスの主要産地から名誉ある騎士号を叙任している。
シャンパーニュ騎士団 シュヴァリエ / ボルドーワイン騎士団 コマンドリー /ブルゴーニュワイン騎士団 シュヴァリエ








