
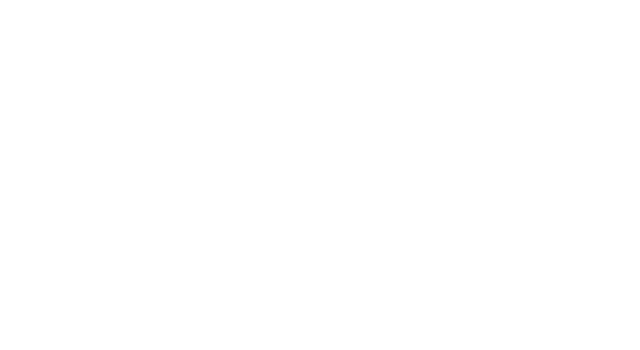
お肌のはりを保つ「はも(鱧)」 はも
名前の由来は鋭い歯で魚を食べることから、「食べる」を意味する「はむ(食む)」とする説と、ハモの姿がヘビに似ることから、蛇の方言と同源とする説があります。
6月~7月あたりまでが旬となります。11月あたりに獲れる物は産卵後に旺盛な食欲を満たし身が肥え、脂が乗ったものとなり、体表が金色を帯びてきます。金ハモや落ちハモと呼ばれ、この季節も旬となります。
栄養素
ハモはたんぱく質が22.3g、炭水化物が0g、脂質が5.3gとなっており、ビタミンではビタミンD、ナイアシン、ビタミンB12、ミネラルではリンが比較的多く含まれています。
カロリーは100gで144kcalのカロリー。
皮にはコンドロイチンが多く含まれており、皮膚のハリを保って老化を防ぐ効果が期待できます。
ハモの栄養成分(可食部 100g あたり)
・ビタミンD・・・5μg
・ナイアシン・・・3.8㎎
・ビタミンB12 ・・・1.9μg
・たんぱく質 ・・・22.3g
・リン・・・280㎎
効能・効果
ビタミンB12:体内で赤血球が作られる際に必要なビタミンです。不足すると貧血を引き起こします。また、睡眠のリズムを整えるホルモンを体内で作られる際にも必要となります。
ビタミンD:カルシウムとリンの吸収・代謝に関与血中濃度を一定に保ち、骨や歯への沈着を促します。骨や歯の形成の他、がん細胞の増殖を抑える免疫細胞の活性化を促します。
ナイアシン:体内で重要な役割を持つさまざまな酸化還元酵素の補酵素として、三大栄養
素などの代謝に関わり、神経の働き、皮膚の健康を維持する働きがあります。
リン: 体内で糖、脂質をエネルギーとして消費する際に必要となるミネラルです。また骨、歯等の形成・代謝に重要な役割を果たします。
東洋医学的側面
・寒熱:寒(体の熱を冷ます)
・昇降・収散・潤燥:潤(体を潤す性質)
・臓腑:秘
・五味:甘(補い滋養する作用)
・毒性:(皮)有毒、(加熱)なし
栄養素を上手に摂るための保存方法と調理方法
ハモは骨切等下ごしらえが難しく一般家庭ではなかなか調理をする機会がない魚だと思われますが、ボタンハモの他、天ぷらやかば焼き等とても美味しい料理が数多くあります。料理屋さんで頂く他、下ごしらえが終わった新鮮なハモを手に入れる機会があれば是非挑戦してみて下さい。










