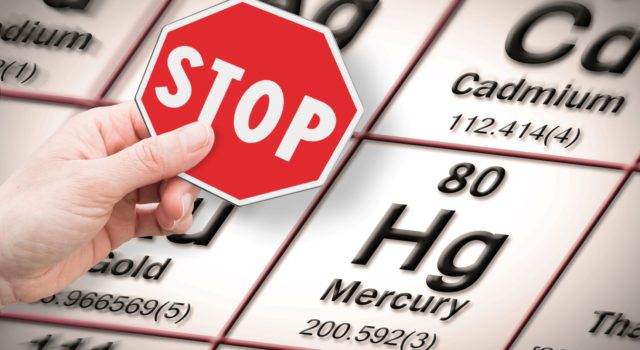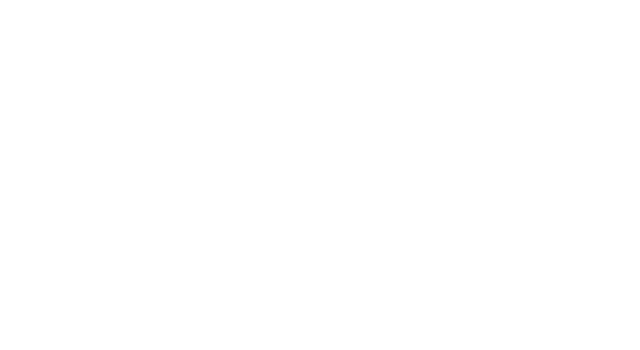
ヨーロッパのアンチエイジング学会でマイクロプラスティックについて考える
DR大友はヨーロッパのアンチエイジング学会に参加するためにモナコに来ています。
この学会はアンチエイジングの世界では最大規模でEU圏内はもちろんのこと、ロシア、中東諸国、韓国や中国など世界中からドクターや製薬会社などの人々が集っています。
一般的にヨーロッパの学会では予防医学や最先端の医学というよりは日々の生活がどうしたら楽しめるのかということに主眼を置いている印象があります。
ヨーロッパでは日本ほど内容は充実はしていないものの、基本的に皆保険制度なので病気なのに病院にかかれないような事態になることがないからだと思います。(プライベートドクターであれば別ですが、通常は日本のように予約をしないで出かけてもすぐに診てもらったり、専門医を選んだりすることは難しいようです。)
ちなみにアメリカはご存知の方も多いと思いますが、医療費がとっても高いのでお医者さんにとっても患者さんにとっても如何に病気にならないかということが最大の興味の部分でもあります。
そのためアンチエイジングといっても予防医学の側面が強い印象があります。
またテクノロジーを重視しているのもアメリカのアンチエイジングの特徴。
再生医療やVR(バーチャルリアリティ)、AI(人工知能)などのトピックが活発に議論されています。

さて今回の発表で一番面白いと感じたのは有害金属、海洋汚染の話。
ヨーロッパでは農薬が食事に含まれていることを非常に気にしている人が多いので、どんな小さなスーパーに出かけてもBIO(オーガニック)認定されている商品が必ずといって良いほど陳列されています。
有機JASの商品を探すのが難しい日本とは大きな違いですね!
一般にはまだ海洋汚染のお話しは馴染みがないのかなと思っていましたが、滞在中にタクシーの運転手さんをはじめとして複数の方から海産物はプラスティックや水銀が含まれているから食べるのは極力控えているという話をしばしば耳にしました。
健康寿命が長いモナコの人が如何に食の安全に気を使っていることが良くわかるエピソードだと思います。

海洋汚染の一つであるマイクロプラスティック問題についてご存知ない方も多いと思いますので少しまとめてみます。
プラスティックが海に廃棄されると砂浜や岩で細かく細かく削られます。
こうして生じる非常に微細なプラスティック(マイクロプラスティック)はプランクトンと同じくらいの大きさになり小魚が食べることになります。
この先は食物連鎖に従って徐々に小さなお魚が大きな魚に食べられて、その大型のお魚にもプラスティックが蓄積されていくことになります。
最終的にそうしたお魚を食べた人間にもプラスティックの成分が体内に取り込まれることになります。
体内に取り込まれたプラスティック、つまり石油成分はエネルギー代謝やアドレナリンなどの神経伝達物質の合成に影響を与えます。
昔から電子レンジで温めた際のプラスティックの悪影響は話題になることはありましたが、健康に良いとされてきた青魚を食べてもそうしたことにも気をつけなくてはいけないご時世になってしまったのは悲しい限りです。(ちなみにご自身の身体にそうした物質が含まれているのかいないのかは尿検査で調べることができます。)
お寿司、お刺身、焼き魚などのお魚が食卓に並ぶことのない日はないと言っても過言ではない日本人としては、いつまでもお魚を美味しく食べるために『プラスティックのゴミを出さない』、『プラスティックをきちんとゴミとして処理する』ように心がけていきたいですね。
マイクロプラスティック問題や有害金属に関してはまたいずれ詳しくレポートしたいと思います。

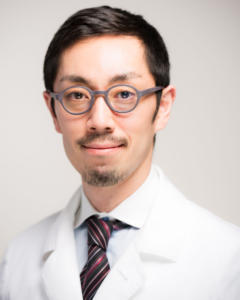
〔大友“ピエール” 博之〕
日本のみならずロサンゼルス、フランクフルト、香港、バンコクに拠点を持ち、個別化医療(precision medicine)を実践している。免疫栄養学に基づいた食事指導、ホルモン補充療法、運動療法を取り入れた治療で定評がある。
・ 医師 日本抗加齢医学会専門医 / 欧州抗加齢医学会専門医 / 日本麻酔科学会専門医
・ 西洋薬膳研究家、シェフドクターピエールとしても活躍中
・ 渋谷セントラルクリニック代表
・ 一般財団法人 日本いたみ財団 教育委員
・ 一般社団法人食の拠点推進機構 評価認証委員/食のプロフェッショナル委員
・ 料理芸術や食の楽しみといった価値感を共有するシェフなどが集う日本ラ・シェーヌ・デ・ロティスール協会のオフィシエ
・ ワインにも造詣が深く、フランスの主要産地から名誉ある騎士号を叙任している。
シャンパーニュ騎士団 シュヴァリエ / ボルドーワイン騎士団 コマンドリー /ブルゴーニュワイン騎士団 シュヴァリエ