
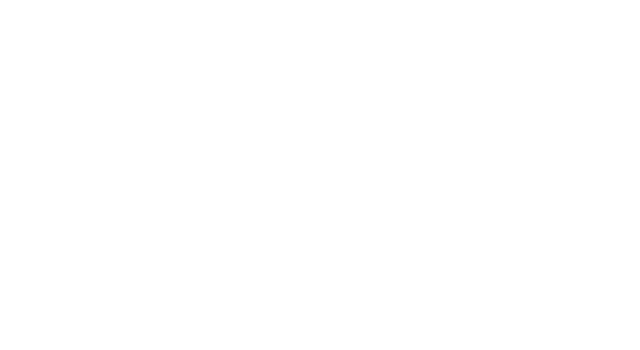
赤い色素リコピンは男性におすすめ「トマト」 とまと
「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるほど、トマトは健康に良い食材とされてきました。
トマトの旬は6~8月です。トマトは本来、高温多湿での栽培には適していないため、品種改良や栽培方法の工夫で、今では一年中手に入るようになりました。
栄養素
トマトの赤い色はリコピンという色素です。リコピンはカロテノイドの一種で強い抗酸化作用があることが特徴です。リコピンの抗酸化作用は、β-カロテンの2倍、ビタミンEの100倍もあると言われています。男性不妊や前立腺がんの予防におすすめです。
抗酸化作用には、老化を促進させ、動脈硬化やがんなどの生活習慣病を引き起こす活性酸素を除去する効果があります。
カリウムは過剰なナトリウムの排出を助けます。
ペクチンは食物繊維の一種で、腸内環境を良くして大腸がんなどを予防します。
フラボノイド系のポリフェノールであるケルセチンは、抗酸化作用を持ち、毛細血管を強化する働きがあります。
トマトの主な栄養成分(可食部100gあたり 1個(中サイズ) 100~150g)
・βカロテン・・・540μg
・ビタミンC・・・15mg
・ビタミンE・・・0.9mg
・カリウム・・・210mg
・鉄・・・0.2mg
・カルシウム・・・7mg
・食物繊維・・・1.0g
効能・効果
- 老化防止、がん予防:トマトに含まれているリコピンには、強い抗酸化作用があり、活性酸素が原因の老化やがんを予防する効果があります。
- 疲労回復:クエン酸やリンゴ酸などの有機酸は、エネルギー代謝を促進し、夏バテ解消や疲労回復に効果があります。
- 血中脂質の改善:トマトに含まれる13-オキソ-9,11-オクタデカジエン酸という脂肪酸には、血液中の脂肪を減少させて、動脈硬化や脳梗塞・心筋梗塞を防ぐ効果があることが報告されています。
- 風邪予防:β-カロテンは体内でビタミンAに変換されます。ビタミンAは皮膚や粘膜を保護し、ウイルスの侵入を防ぎ、免疫力を高める効果があります。
- 高血圧予防:ナトリウムの排泄を促すカリウムの働きにより、血液中の水分量を適切に保ち高血圧を防ぎます。
東洋医学的側面
・寒熱:涼(穏やかに体の熱を冷ます)・寒(体の熱を冷ます)
・昇降・収散・潤燥:潤(体を潤す性質)・降(気を降ろす)
・臓腑:胃
・五味:酸味・甘(補い滋養する作用)・酸(免疫力を高める作用)
・毒性:なし
体に潤いを持たせて、渇きを止める
胃を丈夫にし、消化を促進する
疲労を回復させて、夏バテを予防する
栄養素を上手に摂るための保存方法と調理方法
トマトを選ぶときは、丸みがあり重いものの方が糖度が高くておいしいです。
青いトマトの方が長持ちしますが、完熟して赤くなったものの方が栄養価は高いので完熟したものを購入し、早めに食べるようにするのがおすすめです。
完熟したトマトはポリ袋に入れて冷蔵庫へ保存します。青くて未熟なものは常温で熟すのを待ちましょう。
リコピンやβ–カロテンは油に溶けやすい性質を持っているため、油と一緒に調理することで吸収効率が良くなります。




