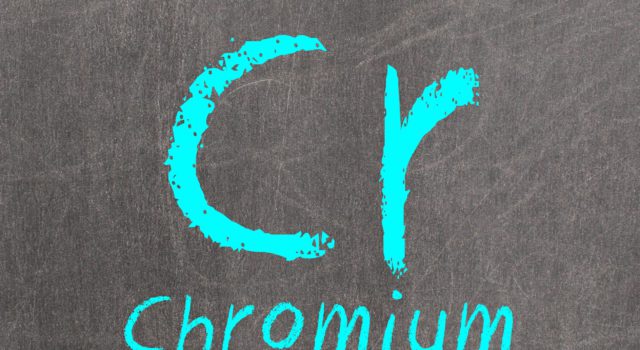
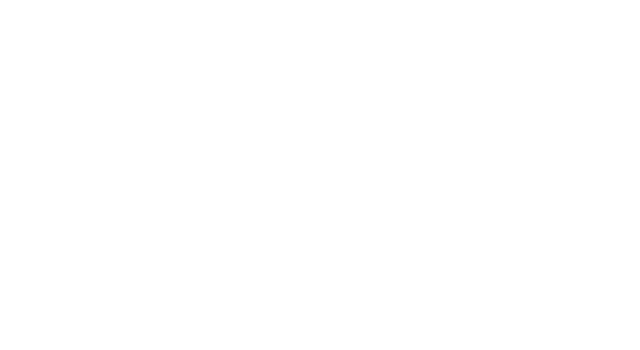
クロム くろむ
クロムとはどのような物質?
クロムは血糖値、血圧、コレステロール値を下げる働きをもつ必須ミネラルです。空気、水、土壌など自然界に幅広く存在し、人間の体内には約2mg存在しています。特に多く存在しているのは、リンパ節、歯、肺で、次いで肝臓、卵巣、筋肉、血液中にも存在しています。
クロムの発見は、1797年にフランスの二コラ=ヴォークランという人によって行われました。この時発見された場所は、シベリア産の紅鉛鉱の中でした。ルビーが赤いのはクロムを含んでいるからだです。
クロムは人が活動するために欠かせない栄養素の1つです。
クロムの効果・効能は?
クロムの主な効果・効能は大きく2つあります。1つが糖尿病を予防する効果、もう一つは動脈硬化、高血圧を防ぐ効果です。以下、それぞれ詳しく解説していきます。
糖尿病を予防する効果
クロムの大きな特徴として、インスリンの動きを高めるというものがあり、これが糖尿病の予防に大きく関係しています。
クロムが糖尿病に有効だとわかったのは1975年のことでした。この時、食品に含まれるクロムにインスリンの働きを助ける効果が見つかりました。
クロムは体内に入ると、アルプシンやトランスフェリンという糖タンパクと結合して全身へ運ばれあらゆる代謝に使われます。
インスリンは糖質をエネルギーに変え血糖値を下げる役割を持っています。食事からとった糖質は、分解され血液に吸収され、インスリンに働きによって全身の細胞へ運ばれます。クロムはこのインスリンの役割を補助する効果を持っています。もしクロムが不足してしまうとエネルギー源であるブドウ糖が全身へ運ばれなくなり、血糖値も下げる事ができなくなります。結果としてインスリン抵抗性を引き起こしてしまいます。
こういった観点から、インスリンの働きを助けるクロムが糖尿病を予防する事につながります。
動脈硬化、高血圧を防ぐ効果
クロムは体内で多くの代謝に関わっています。例えば、コレステロール値の代謝、たんぱく質の代謝などがあります。人間が食事を栄養に変えるにはしっかりと代謝を行う必要があり、クロムの不足によって代謝が正常に行われなくなると、動脈硬化や高血圧になる可能性があります。よって、クロムがしっかりと代謝を助ける役目を果たす事で動脈硬化や高血圧の予防につながります。
クロムの1日の目安摂取量は?
1日のクロムの目安摂取量は成人男性・女性ともに10㎍となっています。クロムを多く含んでいる食材は、あおさやのりなどの海藻類です。日本人は日頃から海藻を多くとっているため、クロムは比較的多く摂取できているといえるでしょう。
クロムの欠乏症や過剰症について
クロムは欠乏症や過剰症になることはほとんどありませんが、過去の少ない例から欠乏症や過剰症でどのようなことが起きるのか見ていきましょう。
クロムの欠乏症
クロムの欠乏症によって起きる症状は、代謝異常、成長障害、脂質・たんぱく質の代謝異常、動脈硬化、脂質異常症などがあります。
クロムの欠乏症が起こった例は1977年のことで、この時発症者は静脈静養だけで栄養を摂取している状態でした。
クロムの過剰症
クロムは吸収率が非常に低いことから、過剰に摂取したとしても深刻な症状になる事はありません。しかし、1日に600㎍から1000㎍のクロムをサプリメントなどで長期的に摂取した場合は、吐き気や下痢、頭痛などの症状を起こす可能性があります。

